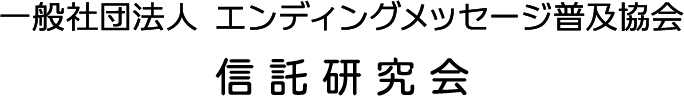信託の法定調書
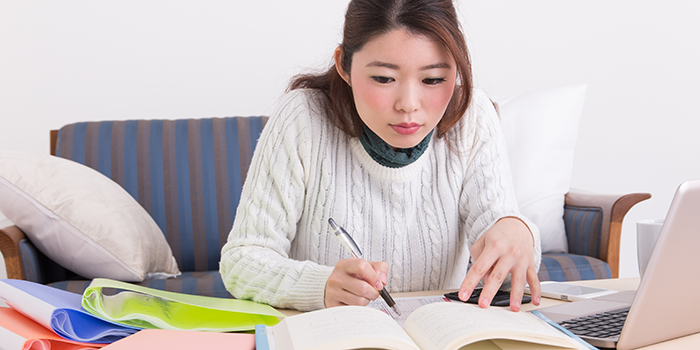
受託者の責務、税務申告を自分で行う方のために
受託者の責務に、信託法定調書の提出があります。民事信託では、面倒な申告業務を外注として、税理士に委託する場合が多く見受けられます。
ただ、家族間の合意によって、将来の認知症対策や親亡き後の障碍者のための福祉信託、また、税理士を通さずに受託者としての役割を行う方のために、解説したいと思います。
信託の法定証書は、「みなし贈与」の発生を税務署が把握するための制度です。
事実上、経済価値が移転しない「自益信託」の場合は、「みなし贈与」が発生しないため、
法定調書を提出する必要はありません。
「他益信託」の場合は、「みなし贈与」が発生します。
ゆえに、受託者は、その翌月末までに所轄税務署へ法定調書、およびその合計表を提出します。
① 信託設定時 (効力発生時)
② 受益者の変更
③ 信託の終了
④ 信託の内容変更
■ 信託財産が50万円以下の場合は法定調書は不要です。( 将来の相続を考慮して、現在価値が
50万円以下であっても、税務署にわざわざ提出する場合もあります。)
どうしても、不得意な方は、申告を含めて、税理士に委託することをお勧めいたします。
▶ 信託支払い調書はここをクリック※国税庁ホームページより
毎年の税務申告
毎年、信託の受託者は、翌年1月31日までに前年分の「信託の計算書」とその「合計表」を作成し、所轄税務署へ提出しなければなりません。
信託計算書は、受益者ごとに作成
受託者に一時的に不動産賃貸料等が入金され、受益者に送金していなくとも、すべての入金があったものとして、申告しなければなりません。
信託計算書には、受益者の住所、氏名、信託の期間、目的、受益者へ交付した利益、受託者報酬を記載します。
収益・費用の明細(損益計算書の情報)と資産および負債の明細(貸借対照表の情報)を記載するだけで、決算書によくある貸借対照表と損益計算書の形式はもとめてはいません。
▶ 信託計算書はここをクリック※国税庁ホームページより
▶ 調書合計表はここをクリック※国税庁ホームページより
受託者の報告義務
受託者は、信託財産に係る会計帳簿を作成し、毎年1回信託の決算書を作成し、受益者へ報告しなければなりません。
会計帳簿の作成は不可欠ですが、資産に変更がなく、資金の出入りだけならば、貼付書類として、信託口座の通帳をコピーし、提出する場合もあります。
原則、「収益の内訳」「費用の内訳」を信託財産の種類ごとに記載しなければなりません。
信託の合計帳簿を作成する目的は、受益者の所得税の確定申告に資する情報を記録することです。
受託者の会計責任
■ 会計帳簿の作成義務
■ 決算書の作成義務
■ 決算書の報告義務
■ 会計帳簿の保存義務
■ 決算書の保存義務
■ 法定調書の保存義務
受益者は、受託者からの報告を受けて、3月15日までに確定申告をしなければなりません。
信託財産に不動産所得が発生する場合
確定申告書に、2つの書類を添付しなければなりません。
① 不動産の青色決算書や収益内訳書
② 不動産所得の明細書 総収入と経費(管理費、修繕費、固定資産税、減価償却費、その他)
注意) 信託財産の不動産の収益が仮に大規模修繕等でマイナスになっても、信託財産以外の収益と相殺することも、繰り延べすることもできません。
受託者は、この点を考慮し、修繕を2年に分けるなり、収益不動産を同じ信託に追加したりすることも必要となってきます。
信託を組成する際には、十分それらのことを検討しなければなりません。
注意) 税法上の義務
信託財産に係る収益の額の合計額がその年で3万円以上ある場合は、受託者は、翌年の1月31日までに信託財産の計算書およびその合計表を受託者の住所地の税務署に提出する必要があります。信託の計算書には、信託財産に係る資産・負債及び収益・費用等を記載しなければなりません。(所得税法227条)
無料相談、会員お申し込み、
民事信託の組成についてのご相談、老後の財産管理、相続、事業承継などのご相談がございましたらお気軽にお問合せください。
ご相談やお問合せのある方は、無料相談フォームに内容を記入して送信してください。
[民事信託を勉強して仕事に生かしたい方]
民事信託を勉強して自分の仕事に活かしたい税理士、司法書士、弁護士、FP、金融業、不動産業、保険業に従事されている方は無料サポート会員にご登録ください。
また、一般社団法人エンディングメッセージ普及協会では、高齢者の問題解決を実行援助できるコンサルタントの要請にも力を入れています。
特に民事信託を熟知したコンサルタントの要請に今後力を入れていきますので、ご興味のある方はプラチナメンバーをご覧ください。