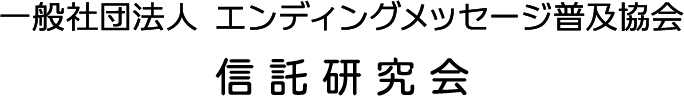福祉型信託について
福祉型信託とは、障害者や高齢者等の生活を支援するために準備しておくための信託です。
民事信託の第一人者である元東京法務局所属公証人遠藤英嗣氏はその著書「新しい家族信託」の中で、福祉信託は「第三の成年後見」として、高齢者や障がい者等の生活を支援する信託であると言っており、「相続に代わる遺産承継」と「後見的な財産管理」に活用できる可能性を論じています。
注意)信託法には「家族信託」や「福祉型信託」という用語や規定はありません。
信託設定の状況において多くの解説書等で「福祉型信託」という呼称を使っています。
注意)信託法には「家族信託」や「福祉型信託」という用語や規定はありません。
信託設定の状況において多くの解説書等で「福祉型信託」という呼称を使っています。
親が障がいを持った子供のために
認知症の配偶者のために
子供が高齢になった親のために
このような人たちが安心して生活ができるように財産を遺したり、財産を管理することができます。
後見制度でも財産管理を行うことはできますが、後見制度では対応しきれない部分まで信託では対応することができます。
ただし、信託は財産管理の制度であるため、身上監護そのものを仕組みに組み入れることは難しいです。
生活や福祉を確保する目的で信託を設定するときは、後見制度の補完の役割として考えることが大切です。
福祉型信託のご相談に対し当協会としては、リーズナブルな管理費の信託会社をお勧めしています。
また、遺す資金を作るために生命保険を活用するなど、ライフプランや相続まで含めた全体的なアドバイスを行ないます。
認知症のマメ知識
・認知症とは
認知症とは「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」をいいます。
・認知症の原因疾患
アルツハイマー病(6割)、脳血管性認知症、頭部外傷後遺症、前頭側頭葉変性症、レビー小体型認知症。
・認知症患者数
平成24(2012)年は認知症患者数が462万人と、65歳以上の高齢者の7人に1人(有病率15.0%)であったが、37(2025)年には約700万人、5人に1人になると見込まれている。
・認知症とは
認知症とは「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」をいいます。
・認知症の原因疾患
アルツハイマー病(6割)、脳血管性認知症、頭部外傷後遺症、前頭側頭葉変性症、レビー小体型認知症。
・認知症患者数
平成24(2012)年は認知症患者数が462万人と、65歳以上の高齢者の7人に1人(有病率15.0%)であったが、37(2025)年には約700万人、5人に1人になると見込まれている。